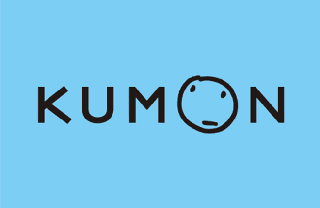企業からの声
グローバル時代を迎えた今、 企業が求める人材、教育とは何でしょうか。 企業の方からお話をうかがいました。

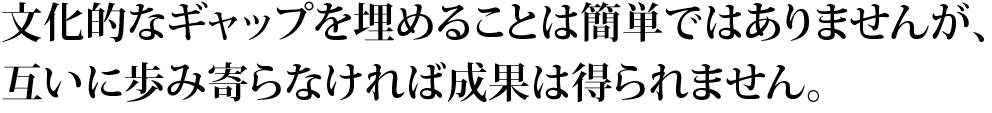
そのため日々、折り合いを模索しながら、意見を率直にぶつけ合う多国籍チームの特性を生かして業務を進めています。
日本政策投資銀行(DBJ)
DBJ Singapore Limited
Chief Executive Officer 兼 Managing Director
長谷井 宏之 氏
1996年 一橋大学社会学部卒業、株式会社さくら銀行(現・(株)三井住友銀行)入行。2002年 日本政策投資銀行(DBJ) 入行、12年DBJ 証券株式会社 業務部長、15 年DBJ Singapore Limited Chief Operating Officerなどを経て23年より現職。
会社概要
日本政策投資銀行(DBJ)
株式会社日本政策投資銀行(Development Bank of Japan Inc.)は、財務省所管の政府系金融機関であり、前身は日本開発銀行、北海道東北開発公庫。DBJグループとして「金融力で未来をデザインします」を企業理念に掲げ、「インフラ再構築・強化」「産業の創造・転換と成長」「地域の自立・活性化」の3領域を重点的に取り組んでいる。
Q.御行の紹介をお願いします。
日本政策投資銀行(DBJ)は、戦後の復興を支援する政府系金融機関・日本開発銀行を前身とし、戦後間もない1951年に発足しました。発足当初から日本の経済・産業振興に努めており、現在もその役割は変わらず大企業や大規模なプロジェクトなどへのファイナンスを中心としたサービス提供を行っています。
民間鉄道の開発や空港・港湾などのインフラをはじめ、高度経済成長期には鉄鋼会社などに産業金融として出融資を行ってきました。その後1980~2000年代初頭には「まちづくり」や都市再開発案件、例えば六本木ヒルズ向けの融資を行い、またバブル崩壊後の2000年代以降は産業再生的な融資や優先株式などリスクのある出資も手掛けるなど、時代の変遷とその時々の社会課題に合わせてファイナンスやソリューションを提供しています。
現在は財務省所管の特殊会社として引き続きインフラや産業向けの投融資を行っていることに加え、近年はサステナビリティ関連の投融資・サービスにも力を注ぎ、単なる経済利益の追求ではなく、社会の器として社会課題を解決する「公共性ある金融機関」であることが最大の特徴です。
Q.どんな人材を求めていますか。
採用にあたり重視するのは、学歴や専攻よりも「公共への貢献意識」、「中立的な視点」、そして「共感力・巻き込み力」です。金融機関は人を動かす力が不可欠であり、時に感化されながら自ら動く行動力が求められます。そのため、相手の立場を理解し信頼を得られる資質が大切だと考えます。
採用の際には、人物重視で選考にはかなりの時間をかけています。結果として6割程度が経済・商学・法学などの文系出身者ですが、理系出身者も4割程度に増えています。今後は海外大学出身者の採用も強化していきたいと考えています。採用は、おおむね通年で行っており、近年は第二新卒の採用にも力を入れています。
Q.入社後に学ぶ機会も豊富だと伺いました。
企業とお客さまに伴走し、融資や投資などあらゆる金融ツールを駆使して成果をともに追求するスタイルを重視しているため、「グローバルな視点」と「地域密着」の両立に力を入れています。社員には地域理解や地域活性化への関心を持たせるよう配属や公募留学などの機会を提供しています。社費留学は近年日本企業のトレンドとしては減っているようですが、当行はむしろ増やしており、リソースに糸目をつけず力を入れています。若手社員は全員1週間のプチMBA研修を受け、経営陣へプレゼンテーションをさせるという取り組みも5年ぐらい続けています。
Q.多国籍・多文化スタッフのマネジメントはどのようにしていますか。
シンガポールオフィスは社員22名中7名が日本人、残りはシンガポール人やインドネシア人など多国籍です。文化的な大きな違いは「行間を読むか否か」です。日本人は言われなくても先回りして動く傾向がありますが、ローカルスタッフは指示された範囲のみを担う姿勢が強く、そのままでは案件が進まなくなることがあります。そのためローカルスタッフに対しては、自分の役割だけでなく「率先してチームを支える姿勢」も求めるようにしています。一方の日本人マネージャーには「(ローカルスタッフには)きちんと全部言わないと伝わらない」という理解を促すようにしており、積極的に巻き込みながら明確な指示を出すように心がけています。
文化的なギャップを埋めることは簡単ではありませんが、互いに歩み寄らなければ成果は得られません。そのため日々、折り合いを模索しながら、意見を率直にぶつけ合う多国籍チームの特性を生かして業務を進めています。
Q.日系企業としてのアイデンティティはどのように大切にしていますか。また、「グローバル」と「地域性・独自性」のバランスについて教えてください。
当行のアイデンティティは「日本の産業や社会に貢献する」ことを基盤としつつ、日本だけに留まることなく世界、とりわけ当行は現地法人としてアセアン地域との架け橋となろうとしている点にあります。政府系金融機関として日本経済への貢献は最大の使命ですが、日本企業も海外と深く関わり、その一部として成長していくことが不可欠です。そのため、世界の持続的発展に寄与すること自体が日本の政府系金融機関としての存在意義でもあります。
具体的には、日本企業と現地企業の協働を積極的に支援し、互いの発展につながる投融資を進めています。例えばシンガポールでは、日系企業と現地企業との共同投資・運営を行うような事業をサポートし、ローカルと日本の双方に利益をもたらす取り組みを推進しています。このように「日本の立場から世界と結び、ともに発展する」ことを使命として日々活動しています。
海外展開においては、日本企業ならではの強みを生かすことを重視しています。現地に迎合しすぎれば、日本の開発金融機関と取引する意義が失われてしまうとも考え、長期的な視点から「真に役立つ提案」を行う姿勢も大切にしています。現地企業やプロジェクトにとっても、日本的なアプローチは差別化要素となり得るため、自分たちらしさを保ちながら顧客との接点を築く方が望ましいと考えています。もちろん言語や文化的な配慮は必要ですが、無理に「バランスを取る」ことだけを目的にはしていません。
Q.女性の活躍と働き方改革について教えてください。
性別に関係なく能力や適性に応じた人材配置を進めています。海外拠点はニューヨーク、ロンドン、北京、シンガポールの4ヵ所ですが、女性駐在員も複数活躍しており、家庭環境に配慮しながら柔軟な赴任形態を採用しています。
育児休暇については「取得が当然」という企業文化が浸透し、男女問わず高い取得率を誇ります。また、若手社員には1ヵ月間のサバティカル休暇(自由に研究や社会活動に挑戦する休暇)を設け、語学学習やボランティア、業務関連の自主研究など多様な活動を推奨しています。現場では欠員調整の負担もありますが、それを通じて「休むことが当たり前」という意識が組織全体に広がりました。結果として、社員は多様な経験を通じて視野を広げ、社内のコミュニケーションも活発化し、ビジネス面での成果にもつながっています。
Q.日本人が他の国籍の方から見習うべき点は。
「自分の意見を明確に伝えること」だと思います。海外では、日本人は面談を何度も重ねても結論が分からないと言われることが多く、意見を短く簡潔に伝える力が求められていると切に感じます。加えて意思決定の速さも重要で、迅速に決断する姿勢はビジネスで特に評価されます。また、海外では事柄と人間関係を分けて考える傾向があり、意見や提案が否定されても人として否定されるわけではない、というさっぱりした感覚があります。そのマインドセットを日本人が学ぶことで、海外でより良い人間関係やビジネスを築けるのではないでしょうか。
2030年代以降は生産年齢人口の減少が深刻となり、このままでは日本だけでは全く立ち行かない時代になります。そのとき大事になるのは語学力だけでなく「自己表現力」で、自分の考えを簡潔にまとめ、相手に理解してもらう力が不可欠でしょう。特に多国籍社会では、曖昧な表現よりも「短く、はっきり伝える」姿勢が必要だと思います。表現力は、家庭や日常のコミュニケーションの中でも養うことができると思いますので、自分の意見を的確に伝える訓練を、日常生活で積むことが大切だと感じます。
Q.海外で暮らすご家庭へのメッセージ
「日本人としてのアイデンティティ」は大きな強みであり、世界で渡り合う武器になると感じます。アセアン地域を対象としたとある調査でも、日本は「住みたい・働きたい国」「長期的に信頼できる国」で上位に選ばれており、日本人らしさはむしろ「個性」として評価されています。現地に過度に迎合し国際人らしさを演じることは、かえって独自性を失う恐れがあるように思います。海外在住中も、日本人としての文化やマナーを堂々と示しつつ相手を尊重することで、異文化の方と信頼を構築していただきたいと願っています。
海外生活では日本に触れる機会が少ないため、一時帰国の際にはぜひ日本の自然や地方に足を運び、さまざまな体験をすることをおすすめします。そうした体験は、将来海外で活動する際に「日本らしい経験」として貴重な財産となり、会話や人間関係の中で独自の強みを発揮する材料になるに違いありません。